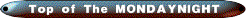<HOT NEWS>J-JAZZストレート(P.113)
東西の社会人ビッグバンドが大活躍!
全国に数百あるといわれる社会人ビッグ・バンドの中でも東京を拠点とする実力派マンデイナイト・ジャズ・オーケストラが、結成30周年を迎え、3枚目のCD「STARTS
FROM M」(写真)を発表した。普段はベイシー・スタイルの演奏を得意とする同楽団だが、このCDでは<モーニン>など頭にMが付く曲にこだわり、それらを様々なスタイルとアレンジで好演。編曲や録音の細部にも気を遣った立派なアルバムにしあがった。詳細は<http://mondaynight.jp/monday/>まで。
一方、西の社会人バンドの雄といえば大阪で活動するグローバル・ジャズ・オーケストラ。米・モントレー・ジャズ・フェスティバルなど海外での演奏も豊富で、優秀なソリストを揃えたガッツ溢れるプレイが人気だ。そのグローバルは1月21~24日までニューヨークで開催される世界最大のジャズ・コンベンション<国際ジャズ教育者会議>に出演するため関西空港を発つ。世界のトップ・ジャズメンやジャズ業界人が集う一大イベントで、日本の社会人バンドの実力を存分に発揮してもらいたい。
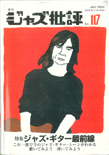
「最期の珍盤を求めて」
小林正家さん、長島輝雄さん、行田よしおさんと語る
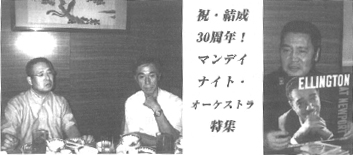
 |
岡村融のホンネ・トーク第64回 学生バンドやお勤めを持っている人の社会人バンドが数多くある中で、今年結成30年を迎えられた、マンデイナイト・ジャズ・オーケストラを紹介したいと思いまして、バンドマスターの小林正家(まさや)さんと、プレイング・マネジャーの長島輝雄さんをお迎えしました。そしてマンデイとは長年のつき合いのある行田よしおさんにお出でいただきました。 |
![]() マンデイナイト結成秘話
マンデイナイト結成秘話
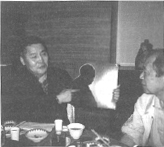 |
| 「マンデイ・ナイトの初めてのレコードのジャケットの絵がすばらしかった。家で額に入れて飾っていたよ」(行田よしお氏) |
岡村:僕は、ビッグバンドが大好きなんで、いろいろ迫ってみたいと思います。僕はポリドール・レコードという会社でジャズ担当していたころ、小林さんは経理部におられて、野球部のマネージャーをしてましたから、僕も野球部員でお世話になりました。20年前、マンデイのデビューアルバム『ブルー&センチメンタル』=1=をアナログで作られたんですが、まさかこんなにすごいビッグバンドになるとは思わなかったね。10年前に2作目のC
Dを出して、この秋にまたCDが出るそうですね。
長島:10年ごとに作品を作ってきたということで、今年ちょうど30年目なんです。
行田:初めてのレコードのジャケットの絵がすばらしかった。家で額に入れて飾っていたよ。
長島:立教でギターをやっていた後輩で、エアブラシを使って絵を描く才能のある人が作ってくれたんですよ。
岡村:最初のアナログの時は行田さんが解説を書かれて、僕も何か書かせて貰ったんですが、あの当時はカウント・ベイシーをメインにやっておられたが、毎年聴くたびに変わって僕は驚かされるんです。今年も杉並で7月13日にありましたね。毎年の社会人のビッグバンドの定期コンサートでは各バンド30分の時間きりないんで、もっと聴きたいと思うんだけど、今年は頭にコルトレーンの「モーメンツ・ノーティス」を持ってきたからね。まさかコルトレーンまでゆくとは思わなかった。あと坂本九ちゃんが歌っていた「見上げてごらん夜の星を」もすごくよかった。あの曲を選んだ理由は何があったの?
長島:マンデイの頭文字のMのつく曲を捜していたとき、車の中で4P.M.とかいう私が知らなかった、アメリカのポップス系のグループが英語バージョンで歌っているのを聴いて、さっそくトランペッターの岡野伸二さんにアレンジをお願いしたら、ボサノヴァとフォービートで素敵なアレンジになっていました。私はボーイングを習い初めたときだったんで、とても良い課題曲になったと思ってます。
行田:きっと長島君のオハコになるね。
岡村:日本にはいい歌曲がたくさんあるのに、ジャズ化されるって殆どないね。
行田:森享さんはよくやったね。松本英彦さんの「りんご追分」、あとなんと言っても鈴木章治とリズム・エースの「鈴懸の径」。
岡村:僕はあのバンドのマネジャーをしていたから、毎日生で「鈴懸」を聴かされて、あれをやらないと客が帰らなかった。
ところで小林君に聞きたいけど、バンド結成のメンバー集めはどうやって作っていったのかしら。そのあたりの苦労話を聞きたい。
小林:僕が中大を卒業した49年の6月でしたか、卒業して楽器が吹けなくなるのは、なんともさみしい事だと感じたもので、その当時のビッグバンド仲間(中央・明治・立教)に声をかけまくり、メンバーを集めたものでした。苦労したのは17名を確保するには、同期の卒
業生だけでは無理だったので、現役の学生さんにも参加してもらったり、ジャズの経験は少ない吹奏楽出身者をバストロに迎えたり、大先輩にもギターやトロンボーンとして参加していただいたりした事ですか。その当時の僕は同期の連中が新入社員として忙しく働いているのとは違い、会計の専門学校に通っていたので、時間的にゆとりがあったので出来たことだと思いますね。それと、譜面を集めるのも大変でした。後輩に頼んで、各大学から何曲も借りてきて、それを当時は写譜をしたんですね。コピーマシンなんてあまり無い時代でしたので。
![]() ビッグバンドの楽しさ
ビッグバンドの楽しさ
岡村:30周年を記念するC DがマンデイナイトのMでうずめた曲を作るということで、どんな曲が並ぶのか楽しみにしています。行田さんとマンデイの出会いは・・・。
行田:ポリドールの経理をやってる人がリサイタルをやるんで司会をやってくれないかと、初めて紹介してくれたのが岡村さんでしたよ。初めてのリサイタルの会場は渋谷のエピキユラス。その後は銀座のヤマハホールで、その後は新橋のヤクルトホールになって。
長島:ヤクルトホールになって15年くらいかな
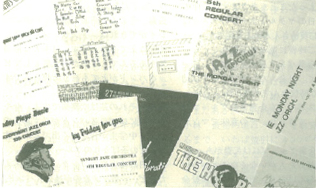 |
| 30年の歴史が刻まれたコンサート・パンフレット郡 |
行田:いい仲間というか、ぐちゃぐちゃ言わなくとも分かり合えるような人たちの集合体だったね。初めてのリサイタルは昭和51年の3月だったけど、お客さんはバンドメンバーの近親者きりいなかったけど。最近はお客さんの顔ぶれがすごい。評論家やプロのジャズ
関係者も多くなった。
岡村:やっぱり30年の重みでしよう。
長島:バンドで我々は稼ぐわけでなく道楽の場なわけ、遊ぶ場がここにあって家庭に戻れば家庭人、仕事で社会人という三つの顔を持っています。遊ぴを人に見せる、その楽しみのチャンスを広げてゆきましようと、15年ぐらい前からベイシ一一本やりでなく、自分たちの楽しみを出してゆきましようという方向ができたんですね。
行田:ゲストも多彩でホーン・プレイヤーだったり、ドラマーだったり、ヴォーカリストだったりと。
岡村:クラリネットの入ったマンデイを聴きたいと思ったこともあったなあ。
長島:花岡詠二さんや若手の谷口英治さんが入ったこともあります。今年の11月29日のヤクルトホールのゲストには、谷口英治さんが出る予定です。このご時世に遊んでる場合じゃないよと、企業バンドが元気を無くしていたりして。社会人バンドにとっては結構大変な時代なんですけどね。
行田:スポーツも企業系のグループは無くなってゆくね。その意味で、マンデイは強い。
長島:企業グループには転勤があって、メインだった人がいなくなるとつらいものがあるけれど、幸いなことに社会人ビッグバンドはネットワークが強く、海外でも日本人が多い所には必ずフルバンがありますから、プレイできるんですよ。うちの初代のコンサートマスターは、香港に行ってそこでフルバンを立ち上げて、5年前我々も行ってジョイントライヴをやってきましたよ。
行田:日本のジャズも今やアラウンドワールドだな。
長島:そこそこ譜面が読めて正確にプレイができれば、アンサンブルが楽しく聞こえてくるんです。日本人は協調性もあるんでしょうが、気質としてビッグバンドがとても合うと思うんですね。
行田:それの基は吹奏楽ですよ。今や中学校にはブラスパンドが必ずあるでしょ。中学生が音がよく出でるんですよ。女の子ばかりのグループもある。全日本吹奏楽のコンクールがあるんだけど、一番ダメなのが社会人バンド。中学生でも島根県出雲がいい。なんでいいのかつて言ったら、世良譲が、俺の出身地だから教えているという、ウソだろう!と言ったけど(笑)。
岡村:小林さんと長島さんの出会いって何がきっかけ?いやー面白いなと思ったのは、昔からトロンボーンとベースは、日本では 10年遅れていると言われたもんだけど、どっちも地味な楽器で若者はあまりやりたがらないのでは・・。最近こそかなりの差は縮まったようだけど、小林君がトロンボーンを選んだ理由は?
小林:中学のブラスバンドでは3年間トランペットでしたが、高校に入ってトランペットを希望したら、なんと大勢いまして補欠みたいな感じでした。先輩がユーホニュームは誰もいないからやってみたらと誘われましたね。同じピストン楽器だし、マーチやクラシックでは旋律が多い楽器だからラッパの補欠よりいいかと思い、ユーホを始めました。ところがこのバンドはジャズもやりますので、その時は当然というか、マウスピースが同じ大きさのトロンボーン担当になったわけです。それから私の地味で着実なトロンボーン人生がスタートしましたかね。なぜか性格までトロンボーンみたいになっていったのがおもしろいです。中大では「スイング・クリスタル」に在籍し、長島は立教で学年が一つ下なんですね。立教の「ニュー・スウイング・ハード」でアルト・サックスを吹いていた吉井君と僕は高校が一緒だったという縁で長島と会ったんだね。ほとんど創立当初からいっしょです。
岡村:長島さんはプレイング・マネジャーとひと言で言うのは簡単ですが、ベース奏者であり、司会もしてしまうし、事務局も一切やられて八面六管の言葉そのもの、存在感がとても大きいと思うんです。モダンのビッグバンドはベース奏者がとても重要なんですが、長島さんのベースはとても強力。ウデイ・ハーマンのチャビー・ジャクソン、スタン・ケントンのエデイ・サフランスキー、カウント・ベイシーだとウォルター・ペイジ、みんな強力でしょ。ドラマーの平野君は去年からみるとすごく変わったね。この間のプレイにびっくりした。
長島:彼が一番変わったかも。いままでの「オレガオレガ」というプレイからフルバンのタイコはメンバーの気持ちを高めるのが大事だという彼のやる気と、ジェフ・ハミルトンとの出会いが大きい。ジェフはよく来日するんで、彼のドラムセットの預かり場としてジェフのワンセットを使わせてもらっている。
岡村:ドラマーによってレパートリーがぐっと広がりますね。
長島:初めはベイシー好きが集まって、ベイシーをやってれば楽しいやと、自己満足のところから始まって、10年後にまたあるきっかけがあったんですよ。
小林:最初の頃はバンドを軌道に乗せるまで、いわば強にメンバーを引っ張って行きましたね。その反動か、もっと民主的に運営していこうという意見が強くなり、その辺りから皆で考え、皆で活動するようになりました。マンデイの民主化の始まりでしたね。今になっては、私はご意見番というか、バンマスというか、何でしょうかね?
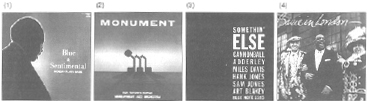 岡村:マンデイのリーダーは誰なのかと思う人がいるはず。
岡村:マンデイのリーダーは誰なのかと思う人がいるはず。
長島:このバンドが30年続いたのは小林がリーダーだからです。それはなんでかと言うと、何もしないからです(笑)。これはすごいことなんです。メンバー全員に参加意識を持たせ、一人ひとりが自分がいなきゃどうなるんだと思わせるには、何もやんないことなんです。
岡村:裏を返すと全部やってるわけ。全員がやりやすいようにまかせてるという読みというか、計算してるんですよ。マンデイのひとたちはベイシーの演奏を臆せずしてきたけど、本物には叶わない。だけど聴く方には「この人たちはベイシーをやりたいんだなー」という気持ちが分かるんだものねー。
長島:ベイシーはこういうことを言いたいんだなー、こういう事をやりたいんだなーと感じても、日本人の我々がやるんだったら違って当然と分ったのは随分経ってからだったですね。
小林:最初はどこまで近づけるかというコピーだったからね。
長島:レコード聴いて、おくれ感を表現しようとするんですが、全然ダメなんです。彼らは譜面もリズムもきっちり分かって、ニュアンスでおくれて吹くんですから。
20年くらい前に新井英治さんという、トロンボーン奏者のクリニックを受けたんですよ。「自分たちが楽しむためには色んな引き出しを持ちなさい。ベイシーの引き出しだけでいっぱいだったらつまんないでしょ。エリントン、ハリー・ジェイムスなど、色んなものがいっぱいあったら、あなたたちも楽しいし、聴く人はもっと楽しいんです」と、分り易い話をする人でした。
その辺りから物真似でなく、自分たちのものを作ってゆくことが出来れば演奏が楽しめるということが分かって、20年目のCDを作った時はオリジナルのアレンジが多くなりました。
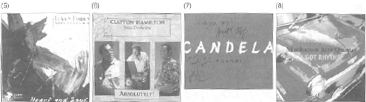 3度目の今年のCDは出来の良し悪しは気にせず、自分たちが楽しめるためにこれを作りました、というものを作るつもりです。今コーチをして頂いているトランペットの横山均さんの影響も大きいですね。
3度目の今年のCDは出来の良し悪しは気にせず、自分たちが楽しめるためにこれを作りました、というものを作るつもりです。今コーチをして頂いているトランペットの横山均さんの影響も大きいですね。
2作目のCD『モニュメント』=2=のときオリジナルなものを作りたいと、一番初めに相談をしたのが岡野伸二さんでした。私たちの能力をよくご存知なので、私たちのできる範囲でカッコよく作ってくれるんですよ。
行田:そうした意味で前田憲男さんが名アレンジャーと言われるゆえんは、そのグループに即したアレンジを書かれるんですね。平均年齢60才のグループは読譜力がすごいとか、若いグループは技量はともかくよく音が出るとか、アマチュアから依頼されるとテープを取り寄せて、自分で聴いて、そのバンドに合ったアレンジをするから、人一倍忙しいんだよねー。みんなこれだけは出来ると思って等しくアレンジしてしまうアレンジャーはダメなんですよ。
![]() ベイシー、リッチ、フラー.
ベイシー、リッチ、フラー.
岡村:長島さんのジャズの聴き初めは いつ頃で誰のレコードでしたか?
長島:高校生の頃、なけなしの小遣いで買ったのは『サムシン・エルス』= 3=か、マイルスの『ウォーキン』か、レッド・ガーランドの『グルーヴィー』の3枚のうちどれかです。どれもジャケ
ットがカッコよかった。 子供の頃ピアノを習っていたんですが、うまい人を知るとこんなのできな いやと止めてしまい、流行り始めたギターも少しは弾けたんだけど、高校の頃自分よりもっと上手いやつがいて、これはギターもダメだと。
 ベースの音って単音で、すぐコピーできて、簡単そうだから大学に入ったら ベースやろうと思ってました、18才の時。大学を選ぶにもフルバンドがみつ
て、ゼミに出なくてよくて、卒論が在 くてという大学を調べたら、立教だ、; たんですね。 立教に入ったら、たまたま4年生のべーシストが抜けて困っていると聞き、
「私ベースやりたいんです」と言ったらその日からレギュラーですよ。べ一三 に初めて触って、これがドで、これがミ だと教わった日からレギ、ユラーです口'
ドレミフアソラシドが弾けるように なって、一週間後に新入生歓迎会があ って、その舞台に出ろと言われて、その頃のベースにはアタッチメントなど
付いてなくて、マイクを近づけて音を捨うわけですが、マイクを出来るだけ遠ざけて、譜面を読めるわけではない。曲の途中で、いきなり全員ぱっと止まって、タイコの人とピアノの人が一所懸命にやってるわけ。私は分かんないから休みなんだろうと。そしたらそれはヒアノソロなんで、ベースはちゃんと弾いてなくてはならないんだと言われて、その程度でもレギュラーになれたんですよ。幸せだったと思います。ベースが合っていたんですね。それから32年やってます。
ベースの音って単音で、すぐコピーできて、簡単そうだから大学に入ったら ベースやろうと思ってました、18才の時。大学を選ぶにもフルバンドがみつ
て、ゼミに出なくてよくて、卒論が在 くてという大学を調べたら、立教だ、; たんですね。 立教に入ったら、たまたま4年生のべーシストが抜けて困っていると聞き、
「私ベースやりたいんです」と言ったらその日からレギュラーですよ。べ一三 に初めて触って、これがドで、これがミ だと教わった日からレギ、ユラーです口'
ドレミフアソラシドが弾けるように なって、一週間後に新入生歓迎会があ って、その舞台に出ろと言われて、その頃のベースにはアタッチメントなど
付いてなくて、マイクを近づけて音を捨うわけですが、マイクを出来るだけ遠ざけて、譜面を読めるわけではない。曲の途中で、いきなり全員ぱっと止まって、タイコの人とピアノの人が一所懸命にやってるわけ。私は分かんないから休みなんだろうと。そしたらそれはヒアノソロなんで、ベースはちゃんと弾いてなくてはならないんだと言われて、その程度でもレギュラーになれたんですよ。幸せだったと思います。ベースが合っていたんですね。それから32年やってます。
岡村:ベイシーも元ドラマーなんですよね。なんでピアノに転向したかというと、エリントンのバンドのソニー・グリーアを聴いて、俺はとてもこんなには叩けないやと、ドラマーを止めたそうですよ。レスター・ヤングもテナー・サックスの前はドラマーだったんですね。
レスターがサックスに変わったわけは、ライヴで終わったあと、お疲れさんと言ってメンバーが帰ってしまう、ドラムだけがステージに残ってしこしと片づけしなくてはならない、俺が目を付けていた女の子を他の人が連れていってしまう。こんな楽器やめた!と言ってサックスに転向したんだって。
長島:楽器やってる人ってみんなもてたいんですよ。数年して、何やっても、もてない奴はもてないってハタと気が付くんですよ(笑)。もてる奴は何もやらなくてももてるんですよ。というのが青春の思い出ですね。
岡村:では長島さんの愛調盤は?
長島:ビッグバンドでの3枚は『ベイシー・イン・ロンドン』=4=かっこいいと思う。ロンドンよりもっと古い「オールド・ベイシー」が好きになってはまり、最近のフルバンドで私が好きなのはクレイトン・ハミルトンバンドです。
これは貴重なサイン入りで日本でもっと売れていいはずなのに=5= =6=。ジョン・クレイトンとジェフ・ハミルトンに出会ったのは、我々にとってものすごくハッピーでした。
コンボの3枚は、ピーターソンの『プリーズ・リクエスト』、私の師匠のマーク・トゥーリアンの入ってるカンデラ=7=、マシューズさんのは=8=マシューズさんと高橋達也さんと共演されたとき目の前で見て、マシューズさんが片手が利かないことを初めて知ると共に、それを感じさせないプレイと人を楽しませることに感激して、生まれて初めてファンレターを送ったら、次の年に招待状を頂いてから毎年来日される度に聴きにいっています。立教の後輩が作っている「100年の孤独」という焼酎を持って楽屋に挨拶にいくのが楽しみなんです。
ヴォーカルはダイアナ・クラール= 9=、クレイトン・ハミルトンバンドで初めて来日し、売れ出す前から観てますので、今や大スターになって何かうれしいです。それとシナトラです。
アイドルにあげたい人は、レイ・ブラウン=10=。クラシック畑ではゲリー・カー=11=です。アメリカ人ですからジャズっぽい曲もやるし、すごく明るいんですよ。アルコでこんなに歌える人っていないと思うほど技量の高い人で、素晴らしいエンターテイナーです。
岡村:小林さんはいつ頃ジャズを聴き始めたの?
小林:甲府一高というのは山梨県で、唯一ジャズをやっていた高校なので、そこでジャズを知ったのです。高校生のジャズというのは難しいことをやらないから、それなりのものきり出来なかったけど、グレン・ミラーやテッド・ヒースが多かった。進学校でしたが大学に行った先輩たちが譜面をまわしてくれたんですね。大学に入ったとき、バディ・リッチのこのレコード『スインギン・ニュー・ビッグ・バンド』=12=を自分の金で買ったのが初めてだったかな。
岡村:バディは譜面の読めない人なのに、あれだけのビッグバンドを持ってたんですからすごい人ですよ。というのは陰のドラマーが3人いたんだそうです。彼は歌も歌うから、ライブでは別のドラマーが叩くわけですよね。彼は新曲に取り組む時は、譜面の読めるド
ラマーに叩かせて、リハーサルをすると1回で全部頭に入っちゃう、1回の練習で「わかったOK」なんだって。信じられないくらい感の強い人で、ものすごく練習の厳しい人だったそうです。
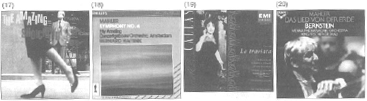 かつてのアレンジャー三木敏悟さんは、国際キリスト教大学に在学中にピックバンドがあって、テナーを吹いていた頃に僕はつき合っていたんで、彼の話によると彼はバディのリハーサルに行ったことがあったんだって。
かつてのアレンジャー三木敏悟さんは、国際キリスト教大学に在学中にピックバンドがあって、テナーを吹いていた頃に僕はつき合っていたんで、彼の話によると彼はバディのリハーサルに行ったことがあったんだって。
行田:シャープス&フラッツが40周年の時、バディのオーケストラが参加して全国公演をやったとき、僕もいっしょに司会者としてまわったんだけど、スティックがドラムの横にいっぱいあって、ミスったバンドマンにスティックがすぐ飛んでゆくんですよ。コントロールのいい投げ方をするんだ(笑)。
岡村:シンバル飛んできたら首はねられちゃう。で、小林さんの愛聴盤は。
小林:私のきっかけ、バディ・リッチです。我々ビッグバンドで好きな作品というのは、『ハヴ・ア・ナイス・デイ』=13=、『ジス・タイム・バイ・ベイシー』=14=。コンボ3枚は『クール・ストラッテイン』
『サイドワインダー』 『アート・ペッパー・プラス・イレヴン』=15=。
岡村:それはマンデイで是非やって欲しい。
小林:アイドルはカーティス・フラー です。『ブルースエット』。ヴォーカルはエラ・フィッツジェラルドです=16=。
![]() 司会のコツ
司会のコツ
岡村:マンデイの司会に行田さんがピッタンコだなと僕が思うのは、マンデイの人たちって真面目だから、どうしても緊張気味になるのね。客席で2時間ステージ観てると、ちょっときつくなる時があるんです。そこへ行田さんが出てきて、ちょろっと一言二言喋ると気分がほぐれるわけ、すると次の曲に別な気持ちで聴くことに入れるわけ、コンサートを生かすも殺すも司会にかかっている部分って大きいと思う。
行田:そんなにおっしゃっていただくほどでもない。マンデイのリサイタルでは生かしたこともあったけど、ズタボロにしたこともあったね(笑)。
長島:私が司会を始めたのはね、行田さんの司会を聞いて、そうかこの手もあるのかと思って、だから私の司会の師匠は行田さんなんです。決して誉めてるだけではないんですけどね。長いこと色んな音楽を聴いてこられた方なんで、含みがたくさんあって、存在!惑があって面白いんです。
行田:自分も中高生時代ブラスパンドでラッパを吹いていて、トランペッターになりたくて、南里文雄に弟子入りしたけど、病気になってトランペッターになることを諦め、そしてジャズの司会をやるようになった。
でもジャズ界にはトニー谷、ロイ・ジェームス、E・H・エリック、油井正一、河野隆次、牧芳雄、本多俊夫、小島正雄氏など上にいっぱいいるわけ。いソノてルヲさんはまだ若かった。とても僕のところに仕事が来るわけがない。色々紹介していただいて、東洋企画、ホリプロ、ナベプロなどで仕事をいただいたので、歌謡曲の人たちとも親しくさせて貰っていました。やっていて分かったことは、アマもプロも関係なく、みんなテンション高くやってますんでね。次の曲にゆく間の2~3分に前の曲の気分を変えなくてはいけなし」その時に「只今の曲は・・・」とかの解説は要らない。今は客の方が知ってるからね。バカを言う方がいい。それを学ばせてもらったのが大橋巨泉さんでした。「ツカさん(原{吉夫}よかったよ・・・今のはー)とくだけるんですよ。不二家ミュージックサロンの専属司会が巨泉さんでした。巨泉さんがやめたあと、僕が2年くらいやりました。ちょっと間違うと手当たり次第ものが飛んできたり叩かれたりして。
その頃の司会はアナウンサーみたいにキレイにやらなければならなかったの。それが一番上手かったのが河野隆次さんだったね。司会でなく解説者。
 |
| 行田よしお司会生活30周年記念リサイタル『夢のまた夢コンサート』(1993年、新橋演舞場)のプログラム |
岡村:そおー。実によどみなくとうとうときれいな言葉で言うわけ。日本人特有のえ一、あのー、そのーが一切ないことではすごい人でした。タテ板に水できれいにほんとにすごかった。河野さんの真似だけは誰もできないだろうなあ一。リズム・エースの専属司会で、全国ツアーで日本中まわったこともあるんですけど、お金に執着のない、宴会では踊りを見せたりという、ハッピーでネアカな人でしたよ。
行田:河野さんと正反対で面白い司会をしたのが油井正ーさんで、徳川夢声のような講談調でね。だからここに油井さんの『じ・あめいじんくVol.2』=17=を持ってきましたよ。
岡村:ラジオで横丁のご隠居さんをやりましたね。
行田:油井さんがご隠居さんで私が八っさんで、あれはむずかしかったですね。知らないふりをして聞き役に徹するのはね。油井さんて役者にもなれた人でしたね。
岡村:横文字の人名と曲名など純日本人風の発音でね。2時間のFMラジオ番組をごいっしょした時も、日本人向けの放送なんだから純日本風英語でいいんだとおっしゃられて。
行田:人名と曲名は日本人風英語でハッキリ言いなさいと、私も言われましたよ。
岡村:外人との会話も日本式発音でやってましたよ。
長島:小林も私も外資系の会社にいてね。会社の公用語は英語だったけど、シンガポールや香港の人のように憶せず喋ることを心がけていました。ジャパニーズ・イングリッシュでも自分の伝えようと思う気持ちが大事なんで、発音がどうのこうのよりちゃんと口に出す。外人は日本人に対して流暢な言葉なんぞ期待してませんし、気持ちが伝わることの方が大事ですから、油井さん流は正解なんですよ。流暢に喋らないと英語でないというのは大間違いですよね。
行田:僕も英語はそんなに達者でないのに、40年間外国のタレントと付き合ってこられたのは、心と心なんですよ。「フロム・ハート・ツー・ハート」ジャズもそうですよね。
岡村:ところで行田さんの愛聴盤は。
行田:私は家ではジャズは殆ど聴かないんですよ。愛聴盤というとクラシックとオペラが大好きで、ベルデイの椿姫=18=、マリア・カラス、マーラーの4番=19=や、9番、バーンスタイン=20=がいいですね。これ私の30周年リサイタルのプログラム(前ページ参照)。
岡村:いい写真があるね。
![]() ビッグバンドの役割分担
ビッグバンドの役割分担
岡村:小林さん、ビッグバンドの役割分担を教えてくれない。
小林:トランペット4~5人、トロンボーン4人、サックス5人にピアノ、ベース、ドラムの3リズムが基本に、ギターが加わって4リズムになったりします。ブラスセクションのトランペットとトロンボーンは1,
2, 3, 4番とほぼ同じ役割です。
1番はリードといってますが、メロディを担当し、2番はアドリブ担当ですが、マンデイのセカンド・トロンボーンは少し違いますね。殆どアドリブやらない、私が担当していますのでネ。3番は結構むずかしい音がありますので、音程面でしっかりしないといけない点で重要な役割です。4番というのはバンドによって違うでしょうが、音域が低く、さらに音程を正確に吹かねばならない。トランペットの4番にアドリブ・プレイヤーを置く場合もありますね。マンデイもそうです。
岡村:サキソフォンにゆくと1番から5番まで。
小林:3番はアルト・サックスで、2, 4番はテナー・サックス、そして5番は低音部担当のバリトン・サックスとなります。テナーはBフラット管で、アルトとバリトンはEフラット管です。
岡村:アルトとバリトンは同じなのね。ビッグバンドではテナーは花のプレイヤーだよね。 小林:そうですね。 2番, 4番のテナー・サックスは両方ともアドリブが自由自在にできて高度な技術と感性が求められる楽器です。
岡村:サックス・セクションのリードは1番アルトで、ソロ・プレイヤーではない。ところがそういう人が主役をやると素晴らしいのね。きれいな音でね、ヒルトン・ジェファーソンとか、グレン・ミラーのウィルバー・シュワルツなど。
小林:パートのリーダーの人はバンドの色を作り出す、リード・ラッパ、リード・アルト、とドラムがバンドの表看板で、ベース、バス・トロンボーン、バリトン・サックスというのは裏御三家と我々は言ってます。この3つがちゃんとしているとすごくいいサウンドに
なり、素晴らしいバンドになると思います。
行田:内外ともにリード・プレイヤーで、アドリブ・ソロを吹く人はあまりいらっしゃいませんね。メロディをきれいに歌うがごとく吹いたのが、シャープス&フラッツの亡きアルト、前川元さん、リード・トランペットの森川周三さんもアドリブは担当されませんでした。
岡村:それとビッグバンドではバンド付シンガーの存在も大きい。マンデイは山本初枝さん。小林さんに山本さんをここで紹介してもらいましょう。彼女との出会い、バンドとのバランスなどその他。
小林:確か85年頃でしたか、先代のヴォーカルの女性が10周年記念レコードを収録した後退団されたので、その後任として入ってきました。水島早苗ヴォーカル教室で勉強されていたせいか、なかなか素晴らしい歌い手さんだと思いました。山本さんはご自身のスタイルをしっかりともっていましたので、彼女の加入によってマンデイも、エラ&ベイシーの曲をたくさん演奏できるようになり、大変貴重な存在になっています。ヴォーカル曲も100曲程ありますので、この20年間でかなり充実してきました。おばあちゃんになっても我々と一緒に歌い続けていると思いますよ。
岡村:そろそろ時間も迫ってきました。みなさんの無人島へ持ってゆかれる宝物はなんでしょうか。
行田:油井正ーさんの東芝レーベルの『じ・あめいじんぐvol.2』=17=、エリントンのポール・ゴンザルヴェスのアドリブが止まらなくなった『アットニューポート』=21=と、『ベスト・オブ・スパイク・ジョーンズ』=22=。
岡村:これが分かる人ってジャズの遊び心の分かる人なんだよ。
行田:談志さんの「やかん」なんか、最後は鳥肌立って落涙だよ=23=談志さん、そこまでやるかって。志ん生の「火焔太鼓」=24=、あと「美空ひばりの山田耕符J=25=、ファーストコーラスが終わる頃は滂沱の涙、端唄なんかも好きなんだ=26=。
岡村:ジャズの仕事ばかりしてると他のジャンルのものが新鮮なのかな。小林さんは?
小林:僕は楽器です。スポーツ感覚で吹くほうなんです、聴く方でなく。
岡村:無人島は電気がなくたって、楽器があれば吹けるし聴かせられる。長島さんは?
長島:私はカミさんと一緒ならどこでもOKです。
岡村:最後に僕のレコードなんだけど、ベイシーのシザックという放送局用の市販されてない、ディスコグラフィには載ってるけど市販されてないからこれだけね=27=。「クレメンタイン」とか「ダニー・ボーイ」とか、歌曲というのかそういう曲ばかりやってるの。このビッグバンドはピル・マクガフイ=28=、イギリスのピアニストなんだけど、スイング系のピアニスト、ビッグバンドなんだけど4,
4, 1, 5。変でしょう、変なビッグバンド。アルト、テナー、クラリネットと曲によって使い分けるマルチ奏者がl人だけ。サックスが4人いない???ピアノがチョロチョロ。小林君、次に逢った時にどういう意味のアレンジか教えてほしい。今日は行田さんとご一緒に会話で楽しんでしまいましたが、このお二方に今後のアドバイスがありましたら。
行田:いつも言っているんですが、プロ・プレイヤーでないんで、どうぞ楽しくひたすら楽しくやってください。ちょっとしたアンサンプルの失敗などは気にせず。好きなことだけ楽しくやってください、ということです。
岡村:今年の11月29日のリサイタルをまた楽しみにしています。30周年記念おめでとう。ありがとうございました。

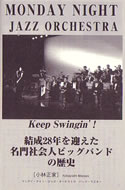
Mondaynight Jazz Orchestra
Keep Swingin'!
結成28年を迎えた名門社会人ビッグバンドの歴史
[小林正家] Kobayashi Masaya
マンデイナイト・ジャズ・オーケストラ バンド・マスター
それは長島茂雄現役引退の年、昭和四十九年六月の事だった。思い出深い街、お茶ノ水の喫茶店「田園」に発起人(中央・明治・立教のOB)があつまり、卒業して社会人になっても「Swing
Jazz」を楽しみたいとの思いから我が「MJO」が誕生した。
今回、「ジャズ批評」の原田氏より原稿の依頼があったのを機に、MJOもそろそろ結成三十年になろうとしているので、久しぶりにMJOの過去を振り返りまとめる事にした。以下70年代、80年代、90年代と三つの時代に分けてみた。
![]() 1974年発足
1974年発足
まず70年代(正確には74年以降)は設立当初の事でもありメンバー集め・譜面の調達・練習場所の確保などの事務的な仕事が大変であったが、そのほとんどを私が担当した。というのも卒業してもまだ学生(会計士目指しての専門学校生)であった私には新入社員には悪い「暇」があったからだ。また、メンバーも我々74年卒の同期だけで構成するのは難しかったので現役や先輩などにも声をかけてなんとかビッグバンドの17名が確保できた。第一回目の練習は74年7月に渋谷にある三浦ピアノのスタジオで行われた。各大学の現役バンドから借りてきた譜面を手当たり次第に演奏して学生時代の延長であるかのように「Jazz」を楽しみ、練習誤は「飲み会」へと場所を移し盛り上がったものだった。MJOはその名のとおり月曜日に練習をするバンドであるがなぜ月曜日だったかというと、当時のコンマスの広浜氏(現在は東京スタイル香港支社長で香港在住)が三越担当でその三越の定休日が月曜日で、そのコンマスの都合にあわせたためだった。他のメンバーにとっても週初の月曜日は比較的残業も少なく結果的には集まり易い曜日であった点もある。バンド活動も順調に進んできた76年の三月に待望の一回目のコンサートを新宿モーツアルトサロンで行った。入場料は飲み物付きで四百円と安く、プログラムは手書きをコピーした粗末なものであった。いわゆるピアノの発表会的な感覚であったに違いない。この時期はメンバーの固定化についての手探りの時代であった。
![]() ベイシー・スタイルを追求
ベイシー・スタイルを追求
さて、80年代に入ると社会人バンドの横のつながりも活発になり81年1月には東京都社会人ビッグバンド連盟が発足されMJOも加盟した。なんでもそうであるが競争心が無いと技の向上は難しかったので連盟への加盟が刺激となり音楽面での充実を目指す方針が採択された。採択と書いたのは、実は設立当初は私がほとんど全てに采配をふるいバンドの運営を行ってきたが「MJOはメンバーが皆で考え合議の上で運営」する方向へと変身したのであった。全員参加の新年総会・月一回のパート・リーダ会議で議論して実行する、まさに会社みたいな組織になった。今思い返せばこれがMJOにふさわしいものであったから今日があると思う。この時期はサックス・セクションを中心に優秀な人材が多く参加して現在まで残っている点も印象深い。中でも当時のコンマスで富安氏(アルト・サックス)の貢献も忘れることができない。彼の加入とサックス陣の飛躍によって音楽面での向上が顕著にみられた。発足当初からMJOのお得意はベイシーであり、好んで演奏してきた。その集大成ともいえる自主制作LP「Blue
& Sentimental」を83年10月に収録して12月の結成十周年パーティーで披露した。このLP、実は某レコード会社の立派な録音スタジオで収録したのだが、そのコストは新人録音という名目で処理したので無償でマスターが出来あがったのだ。メンバーの中にそのレコード会社の社員が二名いたので出来た事かもしれない。(時効ですね)
LPの売れ行きというか頒布状況は自主制作のビッグバンドにしては上々の700枚以上世の中に出て行っている。SJ誌などの媒体で取り上げられたり、当時の司会をお願いしていた行田よしおさんの取り計らいでNHK
FMの番組で放送されたりで、社会人バンドMJOは一躍有名になった(苦笑)。やはりベイシーへのこだわりは強く、その頃のコンサートのコピーも「Monday
Plays Basie」「Memories of Basie」「Keeping Count」などベイシー・サウンドを全面に出してのものだった。ベイシーの売譜面は少なかったので我々はCDから曲をコピーして譜面に起こして演奏していたので他のバンドには無い曲を多くレパートリーに加えることができた。このコピ-はトランペッターでアレンジャーである岡野信二氏にお願いしてきた。尚、岡野氏はMJO初のオリジナル曲「Swingin'
Night」の作曲も含めて30曲以上の楽曲を提供していただき現在でもお世話になっている。余談であるが、88年秋に津田塾大学の学園祭でゲスト演奏し、その後四年間に渡り同学園祭に連続出場していた事がいまだに不思議だ。そして15周年記念の演奏旅行で浜松・京都へと繰り出したのが89年だった。この頃はベイシー作品に没頭した時代でありMJOが音楽面で一歩成長した時でもあった。88年から99年迄コーチをお願いしてきた新井英治氏(トロンボーン)の影響もありベイシー色からの脱皮を意識し始め90年代へと突入して行った。
![]() 結成三十周年に向けて
結成三十周年に向けて
90年6月には船橋でプロのビッグバンド「ゲイスターズ」と競演してその凄さに驚いたものだった。当然だがアマチュアとは違う。特に岡本章生さんのハリー・ジェイムスは圧巻で高橋(トランペット)は岡本さんにほれ込みその後「You
Made Me Love You」をレパートリーに加えてしまった。当時は多くのプロの方々との競演が続きMJO自身よりプロとセットのMJOの場面が多く、又、社会人としての仕事の比重が大きくなってきたためか、節目を乗り切った安堵感からかMJO自身の音楽面で停滞した時代でもあった。この停滞を乗り越えるきっかけが二十周年記念CDの企画だった。93年12月、このCD『Monument』のための収録が某レコード会社のスタジオで二日間行われた(今度は有料)。前回のLPとは異なり、MJOのオリジナル曲やメンバーがアレンジした曲も含めてベイシー以外のバンドの楽曲も取り上げている。演奏も良かったのだが最新鋭の機材とプロのミキサーによる編集でこのCDは本当に良く仕上がっている。MJOのライブと比較すると実によく分かるのが悔しいが。でも1,700枚も世の中に出回ったのは驚きだった。メンバーが固定し、良き指導者やプロの音楽家との共演などで停滞期を乗り切り音楽面でもある程度のレベルまで達した点は正直いって嬉しかった。この経験を生かして最近の数年はMJOのオリジナル・アレンジ曲のレパートリーを増やすように心がけている。また二年前からは新コーチにトランペットの横山氏を迎えて基礎からの音造り取り組んでいて、来年秋に予定している三十周年の記念CD記念い向けて新たな気持ちでスタートしたところである。
駆け足で過去28年を振り返って観て感じる事は、社会人である我々がこのように永く音楽活動を続けられるのは家族・会社の同僚や先輩・後輩などの皆さんの力添えがあっての事と思い感謝するところです。また今後ともMJOへの応援・声援をよろしくお願い申し上げ結びの言葉としたい。
(こばやし・まさや)
 |
トランペッターの数原晋(左)をゲストに迎えた2001年度のリサイタル「ボーイ・ミーツ・ホーン」より、ヴォーカルはMJO専属の山本初枝 |

アレンジ、演奏すべてよし
クレイトン=ハミルトン・ジャズ・オーケストラ「ハート・アンド・ソウル」
The Clayton=Hamilton Jazz Orchestra
「Heart And Soul」
(アレンジャー)John Clayton
(録音)1991年
(レーベル)Capri 74028-2
ビッグバンドの優劣は、演奏技術もさることながら、アレンジの良し、悪しでほぼ決まってしまうことが多い。その点、このビッグバンドは、リーダーであるジョン・クレイトンによるアレンジのすばらしさに負うところが大きい。勿論、ジェフ・ハミルトン(dr)をはじめとして、往年のベイシー楽団で活躍したスヌーキー・ヤング(tp)などビッグバンドの壺を心得たメンバーの演奏は御機嫌スイング感をもたらしてくれる。特にジェフ・ハミルトン、現存するビッグバンド・ドラマーの中でもバンドを気持ちよくスイングさせることに関しては「キング」というべき存在だ。特に「Easy Money」は、聴いている方が踊りたくなるぐらいご機嫌にスイングしている。また彼のモダンなドラム・ソロがフィーチャーされているハードバップな曲「Little Old Lady」からも、このバンドの実力は充分にうかがえる。しかし、このバンドはジェフがいつも僕にくれるメッセージ「Keep Swingin'」の言葉通り、ベイシー楽団に代表される伝統的なスイング感を基調とした音作りが本質。ビッグバンドの豪快さやハーモニーの美しさを充分備えた魅力あるバンドなのだ。
(平野嘉昭:Drummer, Mondaynight Jazz Orchestra)
Monday Night Jazz Orchestra (DCI)
by Jack Bowers
Let's face it, the U.S. patent on Jazz, big-band or otherwise, has run its course. Nowadays, ensembles from all over the world are not only the equal of ours, they are in some cases superior. I've recently heard a number of outstanding bands from Europe and at least three from far-away Japan including the enormously talented Monday Night Orchestra, which has as much to recommend it as any big band I've chanced upon lately except in the area of memorable soloists. On Monument, recorded in December '93, the orchestra opens with "Swingin' Night," written by Shinji Okano (who must be one of Sammy Nestico's most ardent admirers). It sounds almost more Basie-like than Basie himself, right down to the spare Basie-style piano intro and the walking Freddie Green-inspired rhythm guitar, as do the band's scrupulous treatments of Frank Foster's "Shiny Stockings" and Basie's own "One O'Clock Jump." In a similar vein are two numbers popularized by Harry James, "Trumpet Blues" and "You Made Me Love You" (with an unidentified trumpeter setting forth an admirable impression of James on the former). The orchestra's muscular version of Tom Kubis's definitive arrangement of "When You're Smiling" is the most impressive I've heard since the Kubis band first performed it on the album Slightly Off the Ground. Among the soloists (all of whom are unnamed, at least in English), the tenor saxophonist on Henry Mancini/Johnny Mercer's "Days of Wine and Roses" and guitarist on Victor Young/Ned Washington's "Stella by Starlight" easily win the highest marks. The band's female vocalist (also anonymous) is heard on "Hallelujah, I Love Him So," "Just Squeeze Me" and "Am I Blue." She's not bad, although it's clear that English isn't her basic means of communication.The orchestra also offers admirable readings of Horace Silver's "Sister Sadie," Dizzy Gillespie's "Night in Tunisia" and the Burke/Van Heusen standard "Moonlight Becomes You." Recording quality is excellent as is the playing time of 68:32. Some of the Monument Orchestra's favorite songs may be yours as well (several of them are on my short list), and you'll seldom hear them played any more persuasively than this.
Track listing: Swingin' Night; When You're Smiling; Moonlight Becomes You; Shiny Stockings; Hallelujah, I Love Him So; Sister Sadie; You Made Me Love You; Just Squeeze Me; Trumpet Blues; The Days of Wine and Roses; Stella by Starlight; Am I Blue; A Night in Tunisia; One O'Clock Jump. (68:32).
Personnel: M. Takahashi, H. Fujiwara, T. Hatori, N. Teruki, trumpet; T. Fukuzawa, T. Noguchi, H. Kawamatsu, M. Kobayashi, K. Aihara, trombone; M. Sasaki, H. Iseki, S. Suzuki, S. Murase, H. Takahashi, reeds; Y. Kimura, piano; F. Aoki, guitar; T. Nagashima, bass; Y. Hirano, drums; H. Yamamota, vocals.
Contact: Fumitaka Aoki, e-mail admin@mondaynight.jp
www.allaboutjazz.com
Review -> Big Band -> June
学生時代、各大学の音楽サークルに所属し多くの時間をビッグバンドジャズの中で過ごした小林等発起人数名が、「このまま卒業して音楽から遠ざかるより社会人としてのバンドを結成して、ビッグバンドジャズとじっくり付き合っていこう」と学生時代の仲間達に呼びかけてメンバーを集め、当バンドが設立された。初代コンサートマスターの休日が月曜日であり又他のメンバーも集まりやすいことで毎週"月曜日の夜"練習するようになりこの名称となった。
http://mondaynight.jp/monday/
ライブ情報を始めCDやボランティア活動の紹介。世界と日本のジャズ関連サイトとのリンク集あり♪ 1974年結成の社会人ジャズオーケストラ
下記再掲
http://www.wellmet.or.jp/~monday/
ジャズCDやライブ情報、プロフィール、ジャズリンク集など
Mondaynight Jazz Orchestra★★
Access to http://www.wellmet.or.jp/~monday/
1974年6月に結成されて以来毎年の定期コンサートを始めとするライブ活動の他、 精薄者施設やハンセン病患者療養所でのボランティア演奏などの活動を行っている社会人BIG BAND
◆ぶつぶつコメント
ボランティア活動を始め活動の様子がわかるホームページ。 ただ、写真ベースなのが残念。 私も以前マンデイナイト・ジャズ・オーケストラの演奏を聴いたことがあるが、すばらしい。 せっかくだから演奏の一部を聞いてみたい。 ともかく精薄者施設やハンセン病患者療養所など とかく閉鎖的になりがちな場所でボランティア演奏することは入所者にとって大きな支えとなるはずだ。 今後も期待したい。(hiroaki)
モニュメント/マンデイナイト・ジャズ・オーケストラ
最近、村田陽一編曲指揮のマンデイナイト・オケのギル・エバンス流サウンドが人気上昇中だが、 これは20年前から高い評価を得ている社会人バンドの雄マンデイナイト・ジャズ・ オケの2作目であるから、誤りなきよう。 何しろベイシーをやらせたらプロも適わぬ位の特化したレパートリーで、アンサンブル、ソロ、リズムともアマ中ズバ抜けた実力。 ①岡田のオリジナルに聴く ベイシー調のリラックスとペット・ソロのすばらしさにまず脱帽。 ハリージェームスのヒット曲や シルバーの⑥に加え、ボーカル3曲とバラエティーにも富み、 とにかく聴いて断然楽しい。 本当にプロに聴かせたい。
〈瀬川 昌久〉
マンデイナイト・ジャズ・オーケストラ 20周年記念CD
今年六月で結成以来二十周年を迎えた同オーケストラが記念のCDを発表した。 『モニュメント』(副題はOur Favorite Songs)にはオリジナル曲の 「スインギン・ナイト」やオリジナル・アレンジ曲の 「Sister Sadie」等が収録されている。 カウント・ベイシーのスイング感を徹底的に追求して以来、プロミュージシャンをも凌ぐその実力は賞賛に値する。 本作は、アンプレスを基本とするリズム隊と、メンバー全員がソロをとるほかに山本初枝の乗りの良い元気な歌唱もあり、 マンデイナイト・サウンドの魅力をたっぷり堪能できる。 プロの人にも聴いていただきたいCDである。
マンデイナイト・ジャズ・オーケストラ 20周年記念CD
モニュメント~アワ・フェバリット・ソングス
アマチュアながら長くビッグバンドとしての活動を続けている"M・J・O"がその結成20周年を記念してこのCDを制作した。 僕自身も、かつてサラリーマン時代に同好の士を集めてベイシー・バンドをやろうと「クインビー」や「ハヴ・ア・ナイス・デイ」など 練習したことがあるが、結局転勤やら何やらで短期間で終わった。 続けるということは並大抵のことではない。 好きだからこそ、なのだろうが、このCDを聴いていると本当に嬉しくなってくる。 硬さの見られる曲もないではないが、思わず手を叩きたくなる瞬間も数多い。 全国の同好の士に聴いてもらえると良いのだが。〈内藤 遊人〉
マンデイ・ナイト・オーケストラ・コンサート
第19回のコンサートがゲストにトランペッターのエリック宮城(みやしろ)を迎えて行われた。 今回の聴き所は『ワイルド・アンド・マイルド』と銘打ちトランペットにスポットを当てた 第2部でのトランペット・フィーチュア・シーンである。 tpセクションによる「トランペット・ブルース」の熱演に続き、宮城の強力なハイノートが楽しめた「ロッキーのテーマ」が印象的。 社会人ビッグバンドとしては本年で結成20周年の歴史を持つ。 同オーケストラは、ベイシー・スタイルの編成で新人が二人加わったがそのサウンドは変化していない。 村瀬彰吾(ts)、小林正家(tb)、平野嘉昭(ds)等のベテラン組がサウンドをガッチリまとめている。 司会の行田よしおの、いつもの行田節の進行で第一部から緊張感がほぐれアットホームな雰囲気の中で聴く ビッグバンド・サウンドは実に良い。 マンデイをうしろから支えている、トレーナーの新井英治(tb)も加わって演奏を盛り上げ、 また山本初枝(vo)の魅力的な歌も花を添えた。 20周年の特別企画が楽しみである。
(92年11月14日/新橋ヤクルトホール/全17曲演奏)〈須藤〉
Mondaynight Jazz Orchestra
![[]](../../pict/bluemark.gif) 活動年数:19年 活動年数:19年 |
|
![[]](../../pict/bluemark.gif) バンド所属人数:18人 男:17人 女:1人 バンド所属人数:18人 男:17人 女:1人 |
|
![[]](../../pict/bluemark.gif) 平均年齢:38歳(※当時) 平均年齢:38歳(※当時) |
|
![[]](../../pict/bluemark.gif) メンバー構成: メンバー構成: |
|
| Tp:4人 Tb:4人 As:2人 Ts:2人 Bs:1人 P:1人 B:1人 G:1人 Ds:1人 Vo:1人(女) | |
![[]](../../pict/bluemark.gif) 練習場所:代々木八幡セオリスタジオ 練習場所:代々木八幡セオリスタジオ |
|
![[]](../../pict/bluemark.gif) 練習回数:月に4回 練習回数:月に4回 |
|
![[]](../../pict/bluemark.gif) 飲み会回数:月に1回 飲み会回数:月に1回 |
|
![[]](../../pict/bluemark.gif) 主なレパートリー: 主なレパートリー: |
|
| シャイニー・ストッキングス(楽団:カウント・ベイシー/編曲:フランク・フォスター) | |
| モーテン・スイング(楽団:カウント・ベイシー/編曲:ベニー・モーテン) | |
| スウィンギン・ザ・ブルース(楽団:カウント・ベイシー/編曲:ベイシー&エディ・ダーハム) | |
| ウインド・マシーン(楽団:カウント・ベイシー/編曲:サミー・ネスティコ) | |
| ブルー・アンド・センチメンタル(楽団:カウント・ベイシー) | |
| 酒とバラの日々(楽団:デューク・ピアソン) | |
![[]](../../pict/bluemark.gif) 珍しいレパートリー、バンドのカラーとなっているレパートリー: 珍しいレパートリー、バンドのカラーとなっているレパートリー: |
|
| トランペット・ブルース(楽団:ハリー・ジェームス/編曲:ハリー・ジェームス) | |
| A列車で行こう(3拍子)(楽団:ドク・セバリンセン・バンド) | |
![[]](../../pict/bluemark.gif) 91年の活動実績(ライブなど): 91年の活動実績(ライブなど): |
|
| 4月、「ESNOJAZZ」に出演、ゲスト高橋達也さん。 | |
| 5月、春合宿 | |
| 6月、東京都社会人ビッグバンドコンサート出演 | |
| 7月、JABA七夕コンサート出演 | |
| 11月、秋合宿・津田塾大学祭出演(4回目) | |
| 第18回定期演奏会「ヤクルトホール」 | |
| 12月、精薄厚生施設「澄水園」クリスマスパーティー(5回目) | |
| 河口湖リゾートクラブでの仕事(3回目) | |
| 92年1月、千葉県市川市でのコンサート出演、ゲスト細川綾子さん | |
![[]](../../pict/bluemark.gif) バンドのポリシー: バンドのポリシー: |
|
| ベイシー・サウンドに惚れ込んだ連中が毎週月曜日に集まって、おおいに吹きまくり、スイングして、日頃のストレスを解消しています。 音楽の基本路線は、ベイシー中心ですが単にコピーではなく我々マンデーの味付けをしたベイシーサウンドを表現できる様、心掛けています 又我々が楽しむ事はもちろんですが、聴いてくれる人達も楽しんでくれる様にと頑張っています。 |
|
![[]](../../pict/bluemark.gif) 名物なメンバー: 名物なメンバー: |
|
| 2nd Tsの井関は、どんな場所でもストリートパフォーマンスができる、実際に歌舞伎町やN.Y.で1人で吹いて来た。 | |
![[]](../../pict/bluemark.gif) 今後の夢や希望: 今後の夢や希望: |
|
| 93年及び94年にかけておこなう予定の「結成20周年記念企画」(まだ決定されていないが、いろんなアイデアがあります)が無事完了する事。 できる事ならなら、このサークルを子供達の代へと受けついでいきたい。 |
|
![[]](../../pict/bluemark.gif) 代表者:小林 正家 代表者:小林 正家 |
|
l1月30日(土)新橋のヤクルト・ホールでアマバンドの中でも最も秀れた マンデイナイト・オーケストラの第18回目のコンサー卜が開かれた。
ご存知の無い方もあると思うので招介すると、学生時代にサークルでビッグバントに参加していた有志が 「社会人になってもピッグパントと付き合いたい…」の一念で集められたオーケストラで、通常昼間は企業に勤め月曜の夜、 集まって練習をしているので名前もマンデイナイトと名付けられている。
そして年一回その年の成果をコンサートで聴かせているユニークなグループとしてプロも注目している。
その折々ゲストを迎えての演奏を楽しませてくれているが、今回は前東京ユニオンの高橋達也(ts)を迎えて華やかに行なわれた。 このバンドカラーはカウント・ペイシーを迫求しているが、今回はバラエティをもたせてスイングピッグバンドメドレーや ウオルト・ディズニー・ヒットメドレー、などが新たに用意され高橋達也のソロパート3曲をそえてバラエティに豊んだ構成で 会場の聴衆を喜ばせてくれた。
実にシャープなダイナミックなサウンドは、アマチュアとは思えない堂々たる迫力でプロ顔負けのパフーを発揮していた。
会場には油井正一氏その他の評論家も顔をみせるなどこのバンドの良さを物語っているようであった。
司会は行田よしをで軽いジョ一クと進行を受けもちファミリーな暖かい雰囲気につつまれてコンサートが終了した。 筆者は毎年このコンサートを聴いているが、一般のジャズコンサートで味わえぬ感銘をうけるのはオーケストラ全員か ジャズを愛着をもって演奏出来るアマ精神が100%発揮されているからであろう。
l1月30日(土)新橋のヤクルト・ホールでアマバンドの中でも最も秀れた マンデイナイト・オーケストラの第18回目のコンサー卜が開かれた。
ご存知の無い方もあると思うので招介すると、学生時代にサークルでビッグバントに参加していた有志が 「社会人になってもピッグパントと付き合いたい…」の一念で集められたオーケストラで、通常昼間は企業に勤め月曜の夜、 集まって練習をしているので名前もマンデイナイトと名付けられている。
そして年一回その年の成果をコンサートで聴かせているユニークなグループとしてプロも注目している。
その折々ゲストを迎えての演奏を楽しませてくれているが、今回は前東京ユニオンの高橋達也(ts)を迎えて華やかに行なわれた。 このバンドカラーはカウント・ペイシーを迫求しているが、今回はバラエティをもたせてスイングピッグバンドメドレーや ウオルト・ディズニー・ヒットメドレー、などが新たに用意され高橋達也のソロパート3曲をそえてバラエティに豊んだ構成で 会場の聴衆を喜ばせてくれた。
実にシャープなダイナミックなサウンドは、アマチュアとは思えない堂々たる迫力でプロ顔負けのパフーを発揮していた。
会場には油井正一氏その他の評論家も顔をみせるなどこのバンドの良さを物語っているようであった。
司会は行田よしをで軽いジョ一クと進行を受けもちファミリーな暖かい雰囲気につつまれてコンサートが終了した。 筆者は毎年このコンサートを聴いているが、一般のジャズコンサートで味わえぬ感銘をうけるのはオーケストラ全員か ジャズを愛着をもって演奏出来るアマ精神が100%発揮されているからであろう。
COUNT BASIE SPECIAL
結成以来16年間もの長きにわたって、ベイシー・サウンドを追求してきた社会人ビッグバンドがある。 その名は「MONDAYNIGHT JAZZ ORCHESTRA」(東京)。 ベイシーを演ることの難しさ、楽しさを通して実感した"ベイシー音楽"のエッセンスを、 同バンド代表の小林正家さんに明かしていただいた。
【MONDAYとベイシーおじさん】バンドマスター小林正家
我々MONDAYNIGHT JAZZ ORCHESTRAは昭和49年6月に結成された社会人のビッグバンドです。 全員が社会人(内女性2名=p.vo)で平均年齢35歳と少しばかり 「おじさんバンド」に近づいていきていますが、毎週月曜日の練習(セオリスタジオ)を軸に東京を中心に演奏活動を行っています。 そんな我々とベイシーおじさんの付き合い(もちろんベイシー楽団のスコアを通じてのもの)は長く 結成当初から16年になろうとしています。 それというのも我がバンドの目標が「MONDAYらしいベイシー・サウンドの追求」ということであり、 かつメンバー全員がベイシーおじさんを大好きであるということだと思います。 皆それぞれ好きなミュージシャンがいますが、いったん楽器を手にして演奏するとなると、 やはりベイシー・サウンドに勝るものはないようです。
では、なぜ飽きもせずベイシー・サウンドを追っかけているのでしょうか?
それは我々演奏する立場から考えると、譜面づらは比較的簡単であるが実際に演奏し、 いわゆる「あの独特なスイング感・ドライブ感」を表現するには、 我々アマチュアにとってかなり奥が深く時間のかかるサウンドであるがためだと思います。 またベイシー楽団のもつ豪快さと繊細さ及び力強いリズム感が最大の魅力であり、我々の永遠のアイドルでもあるからでしょう。 まさしく我がバンドのライフワークであります。 しかしながら、我々はベイシー楽団ではないので彼らとまったく同じように演奏することができないのは残念ながら事実だあります。 そこで、無理をして完全なベイシー・コピーを目指すのではなく、我々の感性・表現力を加味した MONDAYらしい音作りを目標としてみました。 つまり、ベイシー・サウンドの根底に流れる基本をメンバー全員が等しく理解をして 自分達の演奏に組み込んでいくことが大切であり、その積み重ねにより一つの「バンド・カラー」が確立できるのではと考えました。 このようなアプローチの結果としてベイシー・サウンドに対する大きな挫折感もなく今日まで楽しく付き合ってこれたのでしょう。
次に実際にベイシー・スコアを演奏する時の楽しさや難しさについてですが、我々の経験を基に振り返ってみました。 楽しさや楽しさの両横綱は何と言っても「リズム感」と「アンサンブル」でありましょう。 また難しさの両横綱もやはり「リズム感」と「アンサンブル」であります。
その昔「ALL AMERICAN RHYTHM SECTION」と言われたベイシーのすばらしいリズム・セクションが刻むビートは 今でも我々に心地よい喜びと安らぎを与えてくれる。 抽象的ではありますが、ベイシーのリズムは人間の活動のリズムととても合っているからなのでしょう。 幸いにして我がリズム・セクションは平均点以上のビートを出してくれるので安心して演奏できますが、 時としてセクション・ワークが乱れ不快なリズムになるともう曲は途中で止まってしまいます。 リズムをキープの要はやはりギターでありますが、この要職(刻みだけ)を努める人材不足が悩みです。 ここをカバーするのがベースになりますが、アップテンポの曲では体力との勝負と言われるくらいのがんばりが要求されます。 ベイシーおじさんのピアノもなかなかうまく表現できません。 音数が少なく間のとりかたが絶妙でしかもごきげんにスイングしている。 またイントロのピアノはその曲のイメージを象徴しているためかどうしてもコピーが多くなってしまい、 よけいにピアニスト泣かせでもある。 我がピアニストは苦肉の策として左手は膝の上において、かつ全体のアンサンブルをよく聴きながら演奏するよう試みているようです。 そしてビッグバンドで欠かせないのがパワフルで繊細なドラムであります。 この4リズムががっちり固まった時のビートは正直言ってゾクゾクし気分は最高ですが、なかなか難しいです。
続いてもう一人の横綱「アンサンブル」ですが、1930・40年代はヘッド・アレンジ的な曲が中心であったが、 それ以降ハーモニーを重視したアレンジが多くなり「アンサンブル」の醍醐味を味わうことができるようになりました。 そこで我々ホーン・セクションの登場ですが、総勢13名という大所帯がまとまるのにはかなりの時間が費やされます。
ベイシーのハーモニーはエリントンのそれと比較してそれほど難解でなく、注意深く演奏していれば ある程度納得いくサウンドは出せるのですが、フレーズの抑揚の表現を合わせるのに苦労します。 つまり各個人のアーティキュレーションを統一させることですが、我がコンマスが最もてこずっている問題です。 お手本のレコードを何回聴いて感じを掴んでもいます。
ところでベイシーのアンサンブルを聴くとホーン・セクションがリズムに比べて若干重い(遅れる)と感じられることがよくあります。 これはリード・ラッパが意識的に重く吹く場合は別として、本当は楽器の残響音によってそう聞こえているそうです。 今まではただ重く「のる」ことでベイシーらしさの一つの表現と解釈していましたが、この基本を理解することにより フレーズが引き締まり妙に遅くならず我がバンドのアンサンブルは数段向上したと感じています。 また音の強弱を極端につける手法も忘れることは出来ません。 我々アマチュアにとって小さな音でしっかり楽器を鳴らすことは非常に難しいことですが、ベイシー・スコアでは ここを避けて通ることはできず重要な部分だと思います。 このff(フォルテッシモ)とpp(ピアニッシモ)の使い分けができたときの感激はまた格別であります。
ホーン・セクションのアンサンブルは突きつめていくと、やはり13名の要であるリード・トランペットの力量とか裁量いかんに かかっていると思います。 他12名が基礎がためをし、その上にリード・トランペットが自由に気ままに吹きまくる・・・・・・ このアンサンブルこそ我々が求めているものなのです。 練習量が少ないので時間はかかりますが、達成できた時の喜びはまさにプレイヤー冥利につきるとともに満足感で胸が一杯に なるものなのです。 その上聴いている人に伝わるものがあれば最高です。
以上のような、「リズム感」と「アンサンブル」がうまく重なり合って初めてあのベイシー・サウンドが表現できるのではないでしょうか。
ベイシーおじさんが亡くなって丸五年以上経ちましたが、ベイシーに思い入れの深い我々の心の中ではずっと行き続けている ような気がします。 そして我々の目指す音楽の柱も永遠に変わることなく「MONDAYらしいベイシー・サウンドの追求」となるでしょう。
《マンデイ・ナイト・ジャズ・オーケストラ》
学校は卒業しても、ジャズは卒業しない社会人達
全国いたるところにあるアマチュアのサークルを紹介していく好評連載。 第20回は, アマチュア・ビッグ・バンド界でも有数の実力を誇る「マンデイ・ナイト・ジャズ・オーケストラ」。 昨年は12月のリサイタルを訪れた。●吉村浩二
16回目のリサイタルを開催した「マンデイ・ナイト」
人は、その社会的ポジションに合わせて、いろいろなものとの付き合い方を変えていく。
たとえば学生の街だと、朝からずっとジャズのレコードばかり聴いているということもできる。 これはたまらないよね。 だけど、そういうことは学校を卒業して社会人になるとなかなかできない。 まあ、仕事が終わって夜お酒を飲みに行くモツ焼き屋のことなどを、朝からずっと考えていたりということはたまにはあるにしても。
でも、学校は卒業しても、ジャズは卒業したくないよね。 だから、みんな社会人になっても、その状況に合わせてジャズを楽しんでいるわけなのだけど。
今回うかがったマンデイ・ナイト・ジャズ・オーケストラは、学校は卒業してもジャズはずっと演奏していたい、 そういった人たちによる社会人のジャズ・オーケストラだ。
そのマンデイ・ナイト・ジャズ・オーケストラが、12月9日に銀座にあるヤマハ・ホールで、16回目のコンサートを開くというので、 なんだかうれしくなっておじゃましてみた。
楽しいメンバーとの語らいでバンドの性格を理解
午後4時にぼくがホールに着いた時には、ちょうどゲストのプロ・ミュージシャンの中川喜弘さん(tp), 新井英治さん(tb)を交えてリハーサルの真っ最中。 これが温かい音がして、とてもいい。 そのリハーサルが終わって本番までの時間に、メンバーにいろいろと話をしてもらったのだけど、 その話がリハーサルで聴いたバンドの音のように暖かい。 こういうのって、いいよね。
バンド・マスターの小林さん(tb)は、レギュラーの司会の行田よしおさんの代わりに司会を担当する白井京子さんとの打ち合わせで 忙しくて、話を聞けなかったのだけれど、野口さん(tb), 長島さん(b), 平野さん(ds), そして、高橋さん(tp)が、その分を十分にカバーして話をしてくれた。 特にNTTに勤める野口さんは、本当によくしゃべる。 その日は9日だから、トークの日ではなかったのだけれどなあ。
オーケストラができたのは、1974年の6月。 だから、15年以上も続いていることになる。 野口さんと長島さんは結成当時からのメンバーで、平野さんと高橋さんも、それに近い。 つき合っている年月でいえば、奥さんとのつき合いよりも、"マンデイ"とのつき合いのほうが長いという人もいるのだけど、 それは別に、ジャズのほうがつき合いやすいから、といったことではない、と思う。 よくはわからないのだけど。
こんなに長い間、バンドが続いている理由を聞いてみると、すかさず野口さんが答えてくれる
野口「うち(家庭のことではなくバンド)は、共和制をしいていますから。 各パートにパート・リーダーというのがいて、そういう人たちが月に一回くらいの感じで集まって、運営を話し合うんですよ。 その時に、どういう曲をやろうとかいうことも含めて、いろいろ話し合って決めます。 パート・リーダーは、そのパートの他のメンバーの意見も伝えるわけだし。 それに年末は忘年会、年の始めには総会があって、その総会でその年度の運営方針みたいなものを決めるんですよ」。
そうか、すごいなあと思っていると。
長島「聞いていると、すごいでしょう?でも、ただみんな集まって、飲んでいるだけなんですよ(笑)。 それにみんなそれぞれ他に趣味がありましてね。 たとえば、今ずっとしゃべっている野口は説教だとかといったように(笑)」。
それはそうだよね。 そのことしか楽しみがないと、しまいに思いつめてしまったりして、楽しいんだか、なんだか、よくわからなくなってしまうものね。
「マンデイ・ナイト」長続きの秘訣はやはり参加意識の高さにある
そして、このバンドが長続きしている理由は、まだある。 それは、みんなが何かしら受け持ちのあることだ。 会社でもよくあるよね。"参加意識を高めよう"って。 ああいったことって、みんなで何をやろうという時には、とても大切なことだと思う。
野口「そう、うちは全員参加だから」。
こういうとても明るい人の存在も、バンドが長く続いていることの大きな理由だと、ぼくは信じる。 こんな人って好きだなあ。
平野さんの担当は、メンバーの紳士録などを作ったり、レクリエーションをしきったり、そういったことだ。
この紳士録には、現メンバー17人(OB・OGの数は約40名)に関する、ありとあるゆることが書いてあって、とてもおもしろい。 そのデータによると、平均在籍年数は8年で、既婚率は77%。 これはひょっとしたら、スイングジャーナルの平均的読者像ではないかとぼくは思う。 そして、平均体重や平均身長をパート別に割り出しているのだけど、トランペットの人たちは体重、身長とも一番大きい。 逆にリズム・セクションの人たちは、ちょっと小柄だ。 トランペットの人たちは、ステージで一番奥にいるから、ある程度大きくないと目立たないのかもしれない、 リズム・セクションの人たちは、縁の下で支えていづからかもしれない。 あまりあてにはならないのだけれど。
ゲストできている日本のトップ・スタジオ・ミュージシャンのひとり、新井英治さんのことについて聞くと、もちろん、 勝手にみんなを代表して野口さんが答えてくれる。
野口「うちのメンバーの中に、神保町の下倉楽器店に勤めている人がいて、店によくいらっしゃる新井さんと知り合いになったんですよ。 今、お願いして、月に1回バンドのクリニックをやってもらっているんです。 1年半くらいになりますかね」。
そこで、新井さんにお話を聞きに行くと。
新井「ソロになると話は別なんだけど、アンサンブルだと、プロ顔負けというところもあったりするものね。これはちょっとすごいよ」。
これは別に、メンバーの顔の凄さにはプロも負ける、そういったことではなくて、バンドの名前のように、 週1回月曜の夜の練習だけで、こんなに演奏できるというのは素晴らしい、そのように新井さんはおっしゃっているわけだ。
野口さんがリードする会話に、うん、うんと、うれしそうにうなずいている高橋さんのような人がいたり、コンサート会場には、 メンバーの奥さんや子供たちがいっぱいだったり、澄水園という施設でのボランティア演奏もやっていたり、そして、 いつも支えてくれる家族と一緒の慰安旅行を計画したり、そういったところから、このバンドのあたたかいサウンドは 生まれてくるのだと思う。
82年から2年半在籍したという本誌の筆者としておなじみの成田正さんも聴きに来られて、コンサートは最高に盛り上がった。 このバンドのサウンドがあれば、どんなに寒い冬も少しもこわくない。 ぼくは、そう思う。
●今月はマンデイ・ナイト・ジャズ・オーケストラ(東京都)
結成15年!全国ツアーも大成功
アッというまの15年だった。
長島茂雄現役引退の昭和49年、今に至るリーダー小林正家の呼び掛けに、中央・明治・立教等の学生バンドOB・現役が集まり 小林バンドとして発足。 2年後、毎週月曜日の夜練習をすることで、マンデイ・ナイト・ジャズ・オーケストラと名のるようになった頃から、 メンバーの気持ちの中で"マンデイ"の存在が段々大きくなってきたような気がする。
今から思えば、最初の5年間はメンバーの固定化とバンドの方向性についての手探りの時代。
次の5年間は現在のコンサート・マスター富安敦も加入しメンバーも充実、ベイシー・サウンドを追求しようという 方向性も確認し合った発展の時代。 10周年記念として約700枚も売りまくったというか、配りまくったLPレコードの自主制作も宴会の酒飲み話から始まったという 勢いのある時代でもあった。
そのレコードがジャズ雑誌には紹介されるわ、NHK-FMのジャズ番組で放送されるわ、 とにかく予想以上の反響に驚いてしまったが、かえってそれで妙に安心してしまったのか、社会人として 仕事の比重が大きくなってきたせいなのか、それから数年間はもう一つ階段を昇りきれないもどかしい時代を迎えることとなった。
そうした中での昨年7月、発足当初から加盟していた日本アマチュアビッグバンド連盟(JABA)の主催するビッグ・バンド・ シンポジウムで受けたtbの新井英治氏の具体的なクリニックは、我々のもどかしさを一掃させるきっかけとなった。 以来同氏に月1回定期的にクリニックを受けるようになってから"音の楽しみかた"を少しずつではあるが感覚として 分かり始めたようだ。 楽しむ時代を迎えつつあるのなら嬉しいのだが・・・・・。
さて、結成15周年目の今年"コンサート・ツアー・イン・ジャパン"という大袈裟な タイトルのもと、だてに長いことバンドやってないゾとばかりに全員の人脈を掘り起こし、左記のようなスケジュールになった。 たとえ全て参加できなくても、共通の達成感があり、いつもと違う人たちの前で演奏する刺激、各地のアマチュア・バンドと ジョイント演奏する楽しさを味わえればとの今回の企画は結果的には大成功であった。
酒を飲まない新年総会、全員によるアンケート、月1回のパートリーダー会議などを通し"全員参加のマンデイ"らしい試行錯誤を 繰り返しながらのこの結果に、我々は秘かな自負を持っている。 もちろん、家族の協力と関係者の好意なしには今の我々はなかった。 この場で最大の感謝の意を表したい。
われわれのこれからの夢はあと15年続けて子供たちの世代と音楽を楽しむこと。 そしてその後も15年続けられればひょっとすると、孫たちの世代と楽しめるかも知れないということ。 われわれにとっての"一生モンのオモチャ"は音楽であり、それを見つける事のできた幸せをつくづく思う。
それにしても・・・・・・・アッという間の15年だった。
アマチュア・ビッグ・バンドとの交流・・・増田一郎(バイブ奏者)
学生アマチュア・バンドとは別に、社会人バンドの動きが活発化しており、中にはプロ顔負けのビッグ・バンドも存在している。 しかしこうした人達の活動はあまり知られていないのが実状だろう。 たまたま鶴岡市のニュー・サウンズ・オーケストラ、東京のマンデイ・ナイト・ジャズ・オーケストラという、 2つの社会人ビッグ・バンドにゲスト出演の機会を得たので、そのサウンドについて記してみたい。 共通点はいずれもベイシー・ナンバーを主力としている事だ(学生バンドもこの風潮がある)。 ただし譜面の入手が困難らしく、写譜ミスの多い海賊版相手に悪戦苦闘している。 その辺りがネックとなっているようだが、ニュー・サウウンズ・オーケストラでは、私の書いた5曲と、 小川俊彦君に依頼した1曲の合計6曲を新たに演奏したが、ベイシー物の難解な譜面より、 アンサンブルの点ではかなりの実力を発揮した。 各セクションにしっかりした人がいるのもこのバンドの強みだろう。 一方東京側ではベイシーもの一偏倒でセマってはいるものの、少し背伸びをしすぎているようにも思える。 各々の実力は平均レベルにあるので、セクションさえまとまればかなりのサウンドになるだろう。 特筆したいのはすぐれたベース奏者がいることで、この人はプロでも即戦力で使えるだろう。 音楽を職業としないこうした人達が、ジャズを根底から支えていることも否定できない事実であり、 多くの社会人バンドとの前向きな交流が、ジャズ発展の一つの要素となるのではなかろうか。
自主制作アルバムを作った社会人ビッグ・バンドの心意気
ジャズ以外のナンバーもあくまで"仕事"と割り切らなければならないプロに比べて、アマチュア・ビッグ・バンドは 自分たちの好きな音楽をじっくり演奏できる点で幸せかもしれない。 特に近年、学生ビッグ・バンドの成果には目ざましいものがあるが、さて毎年卒業していく学生たちははどうしているのだろうか。 社会人として1~2年も過ぎれば昔の情熱が甦ってきて、仲間と共にバンドを結成してジャズを楽しんでいる人も多く、 各職場単位で作っているビッグ・バンドも多い。 そんな中でも74年に結成以来、様々な会社から愛好者が集まって活動している東京の"マンデイナイト・ジャズ・オーケストラ"が、 結成10周年を記念して自主制作アルバム「ブルー&センチメンタル」を作った。 練習日が月曜の夜ということからその名を付けたという同ビッグ・バンドは、カウント・ベイシーを中心とした4ビート・ナンバーによる 伝統的なビッグ・バンド・サウンドを追求している。 特に昨年は、ベイシーをとことん追求するという活動方針もあり、その成果として今回のレコードでもタイトル曲の他、 <ディスコモーション><イン・ア・メロー・トーン><サテンドール>など全9曲をベイシーのレパートリーでそろえている。 アマチュア・バンドの弱点ともいえるソロイストも充実しており、よくまとまったサウンドに 社会人バンドの心意気が十二分に感じられる。
Mondaynight Jazz Orchestraのリハーサル
5月3日から3日間『3361 BLACK』はビッグ・バンドの厚い音でにぎわった。 アマチュア・バンドのマンデイナイトの連中がリハーサルにやってきたのだ。 家族を持つ社会人がリハーサルのため連休の3日をつぶすという熱意にまず感動する。
リーダーの小林正家(まさや)氏はポリドールで経理を担当し、トロンボーンを吹く。 彼の話を聞くことにしよう。
「もとはといえば、学生バンドにいた連中が、社会人になって楽器をはなせなくて、昭和49年6月にバンドを結成しました。 学生バンド仲間で交流があったものですから、中央、明治、立教の連中が中心になっています。 ほとんどが会社員、公務員です。 練習は週1回の月曜、「代々木八幡のセオリ・スタジオ」を使っています。 2年前から東京都社会人ビッグ・バンド連盟に加入、この定期コンサートに出ています。 うちの定期コンサートは年1回エピキュラスで行っています。 同メンバーで、できるだけ長続きさせたいし、アマチュアで音楽的に日本一のバンドを目指しています。 ここ『3361 BLACK』のように、マスターがジャズに理解のあるところで集中的リハーサルができるのはうれしい。 みんなよく集まってくれますよ。 東京から近いですから、ほかのバンドでもでいぜい利用されるといいのではないでしょうか」
「フルバンドの魅力?誰かがいったようにスイングがなければ意味がないってこと。仕事で張りつめてたものが楽器を吹くと開放される」 という小林代表はトロンボーン奏者である。
昭和49年 大学のバンド仲間が集まって結成して以来18人の顔ぶれはほとんど変動なし。
平均年齢28歳 ボーカルとピアノが女性。
カウント・ベーシー それが彼らの神様だ。
毎月曜 レッスンを重ね 年1回コンサートを開く。
結婚式やダンスパーティーで演奏もするが 目指すはあくまで音楽性の追求。
東京都ビッグバンドの一員で 専門家からの評価は高い。
"日本一のアマ・バンド"の夢にまっしぐら。